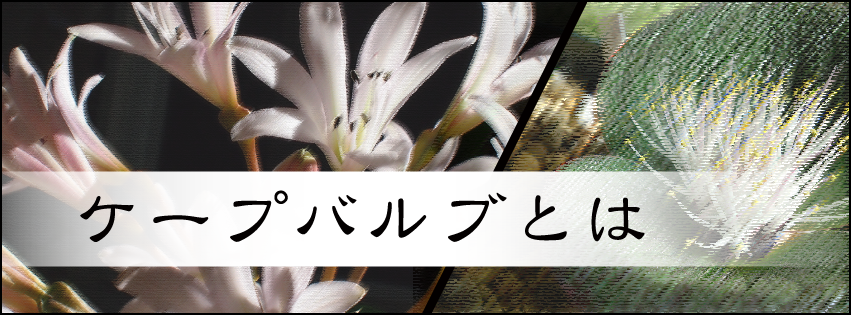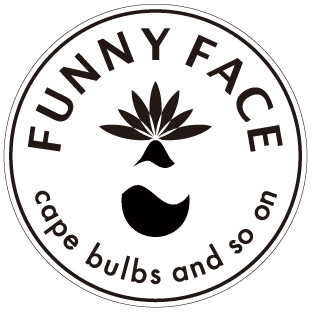2017/11/07 00:10
今は昔、博士と助手が見たこともない植物を発見しました。
その植物は、大きな種のような、いや小さな球根のようなものをたくさん持つ不思議な植物でした。

博士:「これは新種の植物のようだから、名前を付けよう。どうやらドリミア属のようだ。」
助手:「これがドリミア?ハオルチアっぽいです。」
博士:「君、今なんて言ったのかね?」
助手:「えっ?『ドリミア?ハオルチアぽいです』ですか?」
博士:「ドリミア ハオルチアぽいです…」
助手:「ええ。ドリミア ハオルチぽいですです…」
博士:「よし!この植物の名前は"ドリミア ハオルチオイデス(Drimia haworthioides)"にしよう。」
かくして、ハオルチアっぽいことからハオルチオイデスという名前になったのでした。めでたしめでたし。
…
……
この話はフィクションです(念のため)。でも「ハオルチオイデス」が「ハオルチアっぽい」という意味なのは本当です。
植物には頻繁に登場する名前やルールがあって、いくつか知っておくだけでも役に立ちます。「~オイデス(~oides)」は、「~っぽい」という意味になります。ラテン語と日本語が似ているのは完全に偶然だと思いますが、覚えやすくていいですね。有名どころでは「オトンナ ユーフォルビオイデス(Othonna euphorbioides)」があり、これはオトンナ属のユーフォルビアっぽいやつという意味になります。
ところでこのドリミア ハオルチオイデスを見て、「全然ハオルチアに似てない…」と思った方はいませんか?もしそう思ったなら、ハオルチアの自生地の写真を検索などして見てみてください。
きっと「このハオルチア、ドリミアっぽいです…」と思わず言ってしまう姿が見つかることでしょう。
きっと「このハオルチア、ドリミアっぽいです…」と思わず言ってしまう姿が見つかることでしょう。